 今日は中津市の八面山へ。 今日は中津市の八面山へ。
結構前から登りたいと思ってて後回しになってた山。
国道10号から見える特徴的な山容が気になってました。
卓状溶岩台地(メサ)ってやつですね。
ちなみに、どの方向から見ても同じ形に見えるから八面山というらしい。
 八面山荘前の駐車場。90台駐車可。 八面山荘前の駐車場。90台駐車可。
奥に見えるのは北峰かな。
 よく整備されてます。 よく整備されてます。
いたるとこにベンチもあり良い感じ。
 修験の滝へ寄り道。 修験の滝へ寄り道。
ちょっとだけ凍ってる。
 車道に出ました。八面山園地。 車道に出ました。八面山園地。
ここが北峰になります。
 天空の道展望所。 天空の道展望所。
中津市街地が目の前です。
周防灘の奥には山口県まで見えます。
車で来れることから夜景スポットにもなってるようですね。
 天空の道を通り箭山神社へ。 天空の道を通り箭山神社へ。
左に見える巨石が御神体なんだそうです。
鷹のクチバシの形をしてます。
 500mほど車道を歩き、山頂探訪コースへ入る。 500mほど車道を歩き、山頂探訪コースへ入る。
小池を経由して山頂へ向かいます。
 八面山山頂に到着。 八面山山頂に到着。
途中、展望ポイント多くて楽しめました。
 山頂から南側の展望。 山頂から南側の展望。
ちょっと霞んでますが彼方に由布・鶴見。
 ぐるっと周って車道終点。 ぐるっと周って車道終点。
200m先にトイレもあります。
ここに自転車をデポして下山に使うのもアリですね。
 山頂探訪コース、あちこちに雑学クイズあり。 山頂探訪コース、あちこちに雑学クイズあり。
(柱の反対側に回答あります)
全体的によく整備された登山道。危険個所無し。
池あり巨石ありクイズあり。ファミリー登山にいいかも。
 小池へ戻ってきました。大規模な工事が行われてる様子。 小池へ戻ってきました。大規模な工事が行われてる様子。
ここからは来た道を戻ります。
大池探訪コースの方も気になるけど、車道歩きが多くなりそうなのでパス。
|
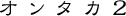
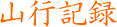
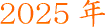






































 長者原から。たまにはロングコース。
長者原から。たまにはロングコース。 森に入ると積雪。
森に入ると積雪。 いつもはガレてて歩きにくい場所でも、積雪あると平坦路。
いつもはガレてて歩きにくい場所でも、積雪あると平坦路。 坊がつる付近は日向で雪なし。
坊がつる付近は日向で雪なし。 山頂手前は雪が深い。
山頂手前は雪が深い。 到着。貸し切り。
到着。貸し切り。 快晴無風。
快晴無風。 法華院山荘に何やら新しいものが。
法華院山荘に何やら新しいものが。 ちょっと霞んでる?
ちょっと霞んでる? マタエから先はチェーンスパイク要。
マタエから先はチェーンスパイク要。 西峰クサリ場。
西峰クサリ場。 西峰。
西峰。 あれ?下山して振りかえると快晴。
あれ?下山して振りかえると快晴。 今日は庄内の里山・冠山。
今日は庄内の里山・冠山。 100mほど歩くと冠山登山口。
100mほど歩くと冠山登山口。 距離は短いものの結構急坂。
距離は短いものの結構急坂。 トラバース気味に北へまわり、大岩を過ぎたとこで直登。
トラバース気味に北へまわり、大岩を過ぎたとこで直登。 山頂の展望はいまいち。
山頂の展望はいまいち。 今季最強寒波到来。
今季最強寒波到来。 牧ノ戸登山口の気温マイナス11度。寒ーっ。
牧ノ戸登山口の気温マイナス11度。寒ーっ。 こんなどかっと降るのは久しぶり。うきうき。
こんなどかっと降るのは久しぶり。うきうき。 久住山。
久住山。 樹氷のトンネル。
樹氷のトンネル。 沓掛山へ寄り道。
沓掛山へ寄り道。 今日は中津市の八面山へ。
今日は中津市の八面山へ。 八面山荘前の駐車場。90台駐車可。
八面山荘前の駐車場。90台駐車可。 よく整備されてます。
よく整備されてます。 修験の滝へ寄り道。
修験の滝へ寄り道。 車道に出ました。八面山園地。
車道に出ました。八面山園地。 天空の道展望所。
天空の道展望所。 天空の道を通り箭山神社へ。
天空の道を通り箭山神社へ。 500mほど車道を歩き、山頂探訪コースへ入る。
500mほど車道を歩き、山頂探訪コースへ入る。 八面山山頂に到着。
八面山山頂に到着。 山頂から南側の展望。
山頂から南側の展望。 ぐるっと周って車道終点。
ぐるっと周って車道終点。 山頂探訪コース、あちこちに雑学クイズあり。
山頂探訪コース、あちこちに雑学クイズあり。 小池へ戻ってきました。大規模な工事が行われてる様子。
小池へ戻ってきました。大規模な工事が行われてる様子。 1か月ぶりの山行。
1か月ぶりの山行。 3月中旬でこの積雪は珍しい。
3月中旬でこの積雪は珍しい。 マタエ。ガスガス。
マタエ。ガスガス。 東峰。
東峰。 牧ノ戸登山口の気温マイナス6度。
牧ノ戸登山口の気温マイナス6度。 御池。さすがにもう融けてますね。
御池。さすがにもう融けてますね。 流氷みたいになってる。
流氷みたいになってる。 中岳。強風。
中岳。強風。 天狗ヶ城。いい青空。
天狗ヶ城。いい青空。 最後に久住山。
最後に久住山。 久しぶりの犬ヶ岳。
久しぶりの犬ヶ岳。 第一クサリ場。
第一クサリ場。 恐ヶ渕ルートの方が、岩場あり滝あり渡渉ありで楽しいですね。
恐ヶ渕ルートの方が、岩場あり滝あり渡渉ありで楽しいですね。 クサリ場もありますが、ほとんどは整備された道。
クサリ場もありますが、ほとんどは整備された道。 大竿峠へ到着。
大竿峠へ到着。 はい、犬ヶ岳到着。
はい、犬ヶ岳到着。 メインディッシュ。笈吊岩。
メインディッシュ。笈吊岩。 今回は経読岳まで縦走する予定で来たのに、雨が降りだしました。
今回は経読岳まで縦走する予定で来たのに、雨が降りだしました。 笈吊峠から先、マイナー山域になるから道が荒れてるかと思ったら。
笈吊峠から先、マイナー山域になるから道が荒れてるかと思ったら。 経読岳到着。
経読岳到着。 三角点は50mほど先の小ピーク。
三角点は50mほど先の小ピーク。 近所の里山へ。
近所の里山へ。 車道を歩き、5分で宇曽山登山口へ。
車道を歩き、5分で宇曽山登山口へ。 宇曽山まではずっとコンクリート道が続くようです。
宇曽山まではずっとコンクリート道が続くようです。 展望ポイント。
展望ポイント。 宇曽山駐車場に出ました。
宇曽山駐車場に出ました。 参拝者無料休憩所。
参拝者無料休憩所。 上宮到着。
上宮到着。 建物裏手に山頂標。
建物裏手に山頂標。 先ほどのトイレの裏手から障子岳方面の道へ。
先ほどのトイレの裏手から障子岳方面の道へ。 細い尾根にのり進みます。
細い尾根にのり進みます。 障子岳到着。
障子岳到着。 登山口に戻ってきました。
登山口に戻ってきました。